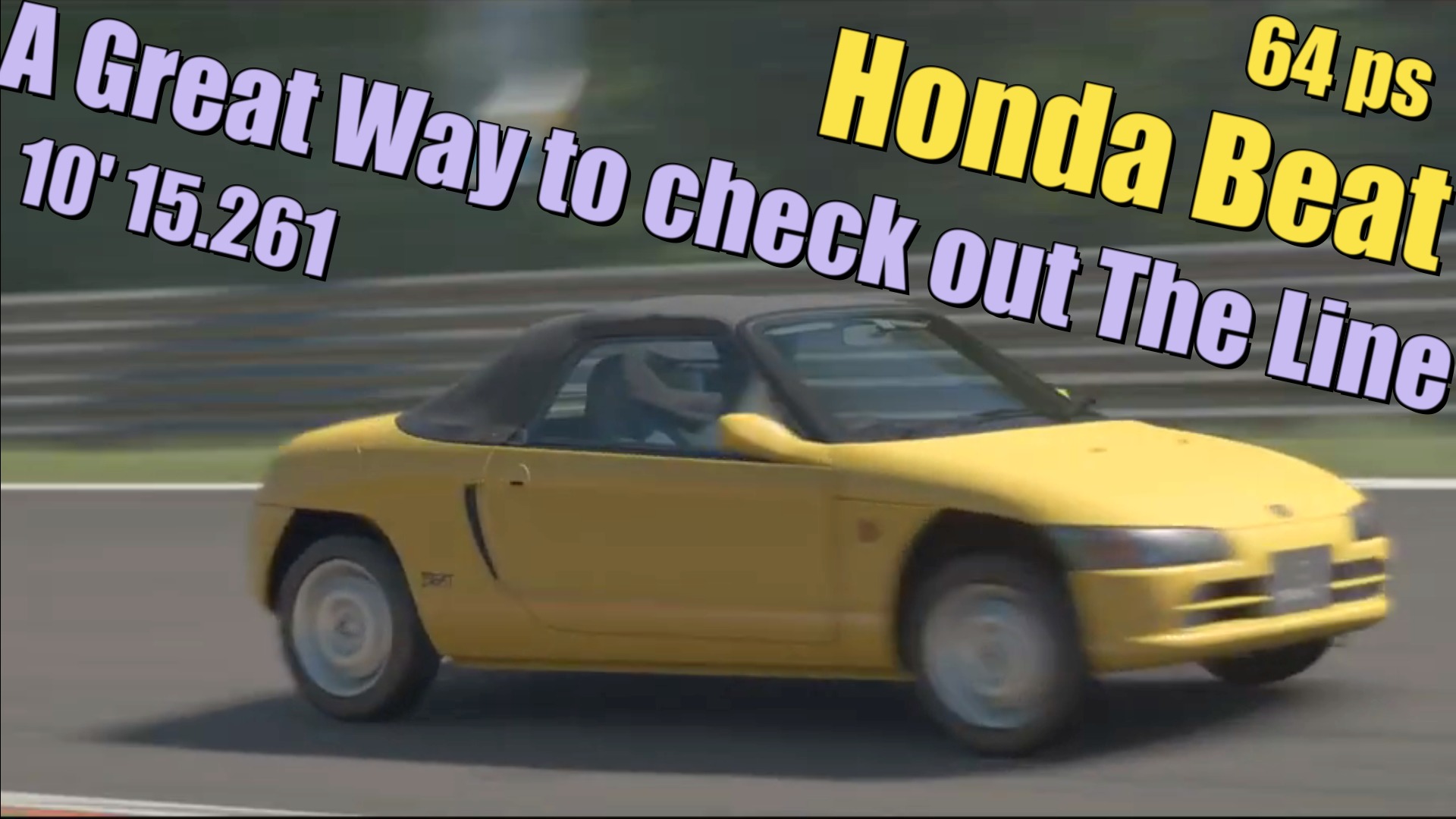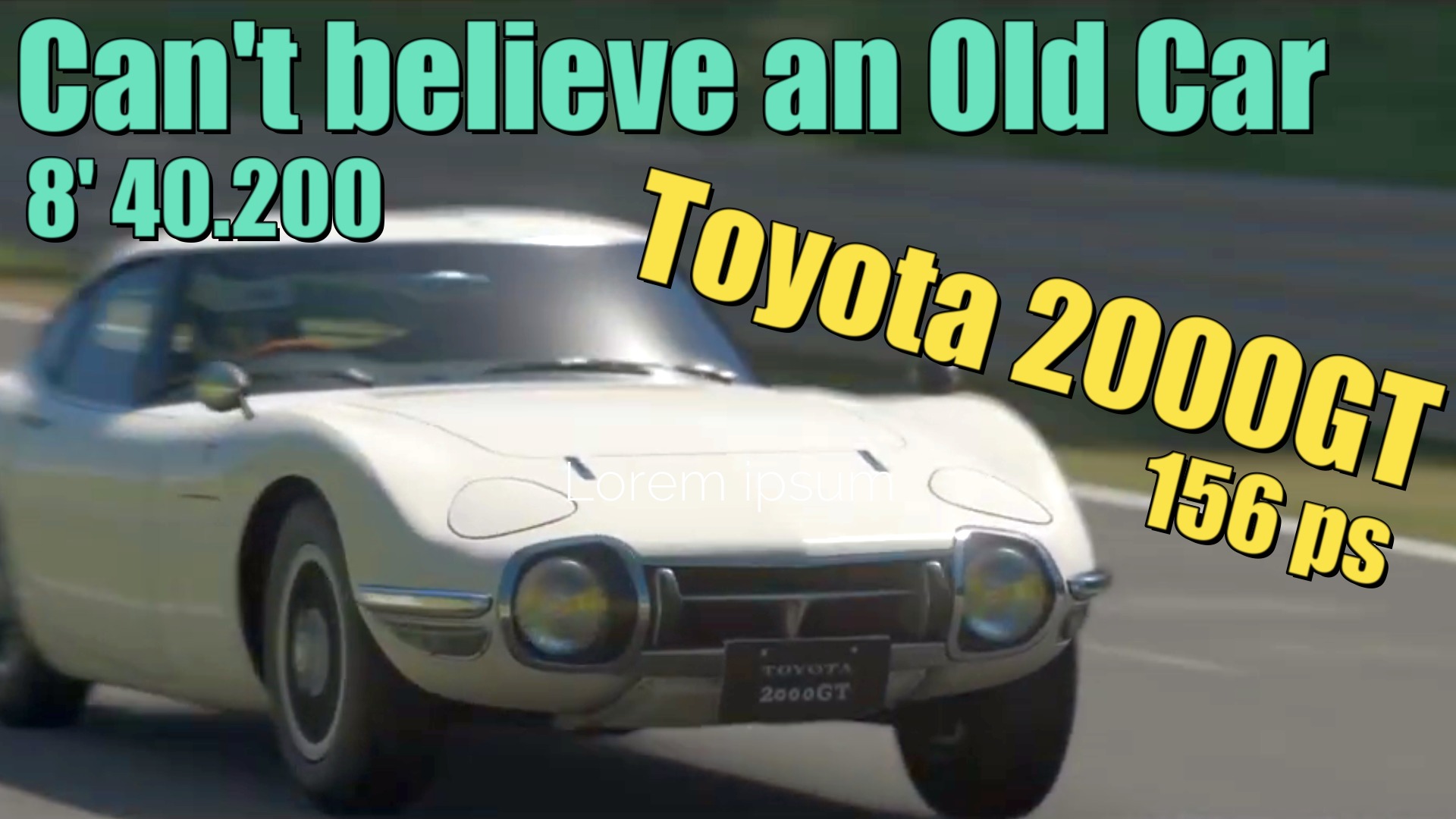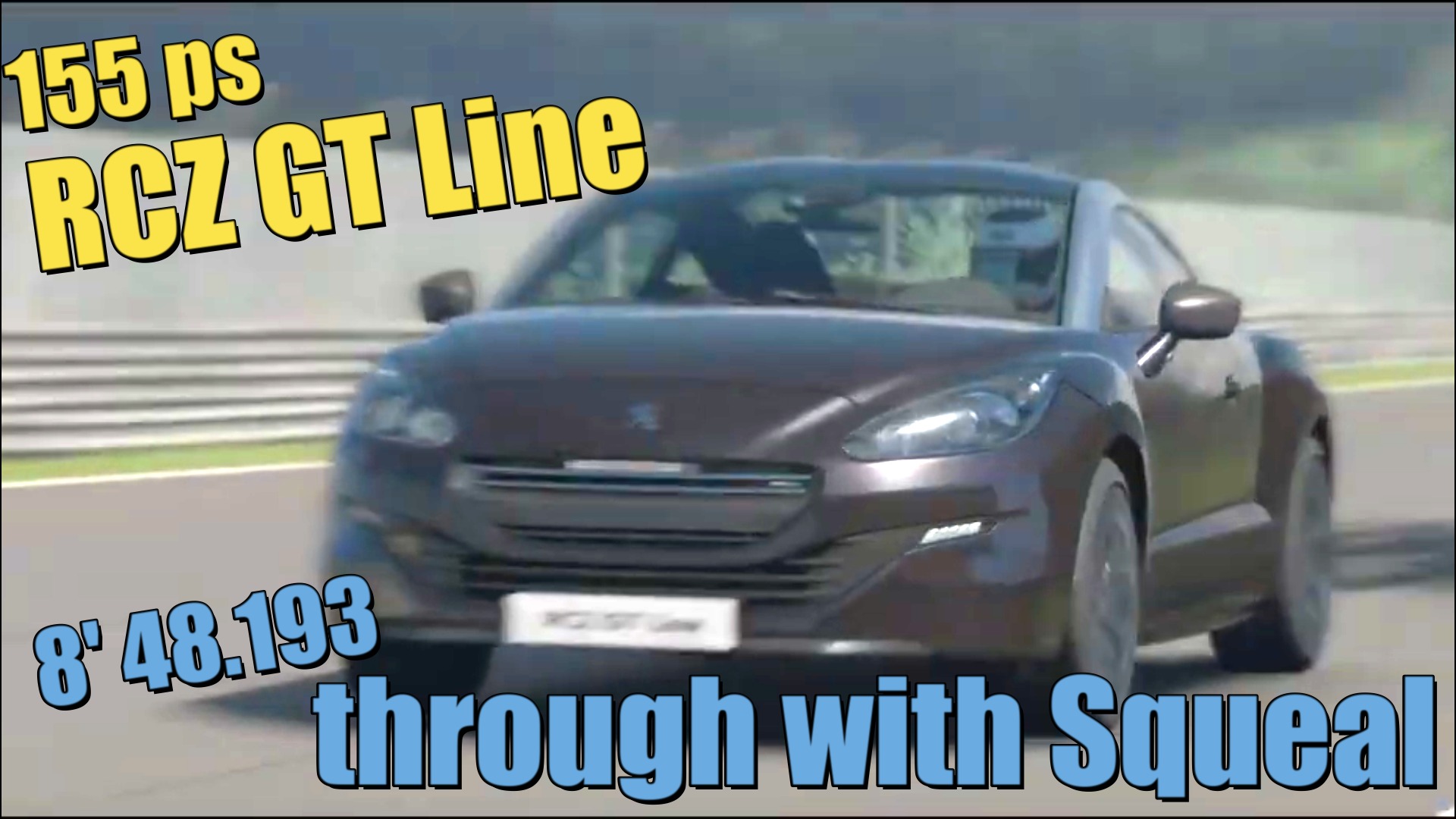【その気にさせる!】
1970年代を代表するV6 2.4L 横置きエンジンのコンパクトMRだ。ステアリングはとても重いが、エンジンは非常に軽快である。高回転域までキャブ車ならではの官能的なエンジン音と共にストレスなく回るこの様は、現代でも十分に通用するフィーリングである。

そして、この車の最大の特徴はハンドリングだ。とてもダイレクトに反応してくれるのだが、リアがとてもナーバスだ。ちょっとでも油断をすると、直ぐにテールスライドを誘発して、とても怖い思いをする。例えば高速コーナーであるSchwedenkreuzでは、リアが外へ高速で流れ出してしまい、極度の緊張感に襲われた。この解決策は、コーナー進入時のターンインで全てが決まると言って良いだろう。ブレーキングをしながらのコーナー進入は厳禁だ。そうでなくても、急激なステアリング操作をするとリアはブレイクしてしまう。肝心なのは、繊細なアクセルワークとステアリング操作との高度に調和されたターンインへのアプローチだ。ここが全てであり、この車のドライビングにおける最も高揚する場面となる。右足のアクセルペダルは、舵の入れ具合とともに繊細にきめ細やかに、リアタイヤの限界付近を探りながら開閉させる。

このコーナリングを一旦得ると、速いだけではなく楽しくてたまらなくなる。実際、Wippermannを過ぎた辺りからgoalまで、多少リアを滑らせながらもとても元気良く走っている姿が分かるだろう。その気にさせる一台だ。